『思考する英文法』
富田一彦 著
大和書房
2025年4月14日発売
A5判
520ページ
【特長】
代々木ゼミナールの重鎮、富田一彦先生が私塾で行っている講義「英文法講座」のテキストを書籍化したもの。
ただ結論だけを示すのではなく、なぜその結論が出るのか、その結論が何の役に立つのかを考えるような解説になっているとのことです。

↓「おすすめ」ボタンを押してランキングに投票!
『思考する英文法』のレビューをお願いします!
- 良かった点、気になった点、難易度などを教えてください。
- 星(★)の数は「参考書の内容」への評価をお願いします。
- スパム対策のため、投稿は承認後に公開されます。
あなたのレビューが、他の学習者の参考になります!
※著者や出版社への誹謗中傷を含む投稿は掲載できない場合があります。
投票数: 1 件
レビューを投稿する | |
ついに登場した、富田英語の真髄である。
長かった、本当に、長かった。なにしろ、本屋開店1時間前から待機し、うずうずワクワク
しながらの思いでいたのでやっと買っただけのことはあった(世間では、これを不審者とい
う)。まぁこれはジョークだが、本当にこの本を望み、長年待ち続けた人々は数知れないだ
ろう。魅了する人を続出し、果ては私塾で英語教室を展開してしまうほどの需要を生み出す
"富田の英語"。その中身は一体なんなのか、その正体がこの本で明かされるのだから、これ
は熱狂間違いなしだ。
この本が出版されるまでには色んな人の声も飛び交っており、これに感謝する人もいれば、
見るに耐えない罵声を浴びせたりする人もいた。え?なぜ見るに耐えないかって?そりゃ
もちろん、的はずれだからだ。
「全体を見る、なんて英語の本質を捉えていない」→なら英語の本質って何か、言語化して
みてくださいな。何故抽象表現で批評するのだろうか。
「日本語で英語を教えるなんてネイティブらしくない」→我々は、日本に住み日本語を母語
とする日本人ですよ。だったら日本語で外国語を学習する方が圧倒的に説明しやすく、我々
もわかりやすいだろう。もしあなたが、英語を母語としているアメリカ人に日本語を教える
として、初めから日本語で全て解説する気ですか?
「Vの数-1=接続詞の数、、、英語に数式を登場させるなんておかしい」→この人は、人の話
を最後まで聞かないタイプでしょう。この数式の証明はちゃんとしているんだから、聞いて
から評価しなされ。
これでも的はずれだが、中にはとんでもないのもあった。
「見開き2ページ(おそらくは、句と節のまとめのことだろう)で富田英語は完結する」→
処理不可能。ただのエアプレイヤー。英語はコンパクトな体系とはいっても、それなりのも
のはある。
とまぁ、この酷い有様だ。もちろんこんなのは無視するのに限るのだが、この的はずれーズ
な感想から三つの教訓を得られる。それがこの本に向き合う姿勢そのものだからだ。
⭐英語の本質は英文法であり、それを理解し運用できれば扱えるようになる
⭐全体を捉え、そこから各部分を処理していくことで英文法を捉えられる
⭐全てを破壊される姿勢とやり抜く努力を持ち合わせる
これの元で、この本と向き合うのが大切なのだ。
では実際にどんな中身なのかを解き明かしていこう。以下に目次の全体像を示す(もともと
富田先生に教わっていた人たちは懐かしくなること間違いなしだ)。
なお ⭐やら ◆やらの説明は一旦置いて欲しい。
⭐序章 抽象化とその目的
A 文型の原理
A-1<SV>文型(第1文型)
A-2<SVC>文型(第2文型)
A-3 <SVO>文型(第3文型)
A-4 <SVO1O2>文型(第4文型)
A-5 <SVOC>文型(第5文型)
A-6 句動詞による文型
A-7 見つけにくい文型
A-8 役割のない名詞(形容詞・副詞)
A-9 受け身を考える
A-10 英語の基本的な語順
⭐A-11 文の要素(S,O,C)と修飾語(M)を区別する基準(品詞と役割の関係)
B 句
⭐B-1 不定詞の三用法
⭐B-2 Ving の三用法
⭐B-3 Vp.p.の二用法
B-4 to V か Ving か
B-5 不定詞の形容詞用法(Mを作るもの)
B- 6 不定詞の副詞用法
B-7 分詞構文の用法
B- 8 準動詞の意味上の主語①基本原則
B-9 準動詞の意味上の主語②例外
B-10 準動詞の意味上の主語③書く場合とその例外
B-11 受動態と準動詞の意味上のS
B-12 名詞+Ving/Vp.p の考え方
B-13 with+S→Pの構文
B-14 感情のV
B-15 Oの欠けたtoVとVing
B-16 疑問詞toV(前置詞+関係代名詞+toV)
B-17 接続詞+Ving/Vp.p.
B-18 be to V の 解決法
B-19 Ving にある二種類の名詞(動名詞と「ただの名詞」)
B-20 Ving+名詞(Vp.p.+名詞)の考え方
C 節
⭐C-1 Vの数-1=接続詞・関係詞の数
C-2 接続詞・関係詞の使い分け①[完全・不完全]
C-3 接続詞・関係詞の使い分け②[節の種類]
C-4 that 節の分類
C-5 as の使い分け
C-6 what の用法
C-7 how 節
C-8 the way 節
C-9 疑問詞+ever節
C-10 前置詞+関係代名詞
C-11 形容詞の限定用法・継続用法
C-12 接続詞・関係詞が多すぎる場合
C-13 接続詞・関係詞が足りない場合
C-14 逃げ遅れた釣り人の構文(分離関係詞)
C-15what/which+役割のない名詞
C-16 if, whether 節
C-17so that の用法
C-18This is why [S+V] & This is because [S+V]
C-19 as long as [S+V] と as far as [S+V]
⭐別表:〔句と節の働き〕まとめ
D 法
⭐D-1 助動詞の基本用法
D-2 推量の助動詞
D-3 客観的に決まる助動詞
D-4 should have Vp.p.の取りうる意味
D-5 助動詞の過去と仮定法
D-6 条件のない(?)仮定法
E 時制
⭐E-1 時制の選択の全体像
E-2 例外的な変化形の使い方
E-3 時制の一致の原則
E-4 時制の一致の破綻
E-5 時制の一致の例外①
E-6 時制の一致の例外②
E-7 動作動詞の現在普通形
F 同じ形の反復
⭐F-1 等位接続詞と同じ形の反復
⭐F-2 比較構文の基礎
⭐F-3 省略の原理
F-4 代用表現(代名詞・代動詞)の考え方
F-5 not only の二つの意味
F-6 B のない比較
F-7 the+比較級
F-8 the のない最上級
F-9 最上級相当表現
F-10 no A [ - er than/ (so) as - as] B
F-11 A no - er than B
F-12 (all)the 比較級+理由/none the 比較級+理由
F-13 比較で使う形容詞・副詞の意味
F-14 比較と紛らわしい等位接続詞
G 品詞論
G-1 名詞と数の諸問題
G-2 固有名詞
G-3 名詞の範囲(冠詞〜名詞)
G-4 冠詞の種類①a/the
G-5 冠詞の種類②所有格
G-6 数量の形容詞
G-7 代名詞
G-8 it の用法
G-9 another - the other - other (s)-the other (s)
G-10 形容詞の性質
G-11 副詞に見えない副詞
G-12 文修飾の副詞
G-13 疑問の構造
H その他の補足事項
H-1 倒置と語順転倒
H-2 挿入の考え方
H-3 否定語の種類
H-4 部分否定
H-5 死んだふり構文(呼応)
H-6 君が全てだ構文
H-7 論理接続の副詞
H-8 前置詞withの用法
H-9 前置詞byの用法
H-10 前置詞ofの用法
H-11 名詞of名詞の攻略法
H-12 前置詞to/for/into/from(out of)/at の使い分け
H-13 「時を示す名詞」につくin/on/at
H-14 前置詞on/inの整理(「時」以外)
H-15 記号の意味
◆H-16 論理のルール
◆H-17 話法
さて、この本を扱う上で最も大切な考え方があるのでまずそれを受け入れてもらいたい。そ
れは、富田英語の正体は"現象別"英文法ということだ。
まぁいきなり言っても「"現象別の"英文法ってなんだ?」っていう人もいるし、ある程度富
田英語に触れている人は「英文解釈とか構文じゃないの?」と思う人もいる。実際、その呼
び名にした方が親しみがあるのでそれでもいいだろう。あえてこの呼び名にしたのは、たま
にいる「英文法と英文解釈(構文)って、分ける必要がありますか?」
という、天才(つまり、ただ勘がいいやつ)or"現象別"英文法の価値を理解できていない人
が言う発言を全力で否定するものである。
世間一般ではいろんな英文法の参考書がある。だがそのほとんどは”単元別”の英文法である。
例えば文型、句と節、時制、、、といった感じな章立てで、解説をしていくものである。もち
ろんこれをやるのは何の問題もないし、その要素はこの”思考する英文法”にもある。ただし
このままで英文法をやった”つもり”でいくと、とんでもない目にあうことになる。それは、”
何に着目していかなければいかないかわからず、読めない”ということである。”単元別”の
英文法の段階で終わっていきなり入試問題に行くことで良く発生する「普段の問題ならで
きるけど、ランダムな文法問題集をやるとできなくなる」「文法をやったはずなのに文章が
読めんぞ」などの理由、それは単純明確で所詮は"単元別"でやってきただけだからだ。そり
ゃ、to 不定詞の単元とわかっていたらto 不定詞に着目し、必要な知識を覚えていたら解け
ますし、読めますよ。でも実際に試験会場に行って問題を読み解く時には単元別にはなって
いない。
「だから英文解釈をやるんだろうが」って?そう、ご名答。ではもう一段階深掘っていこう。
英文解釈とはなんだろうか?「え?文型をとれることだろうが」「重要表現に着目すること
だ」ともし思っているなら、それは”不正確な”解答だ。そう、それでは不十分なのだ。確か
に文型がとれる、重要表現(とはいっても果たしてそれが”本当に”重要なのかわからないが)
をとらえる、これも大切なのだ。ただこれらも含んで大切なのは”出会う英文ごとで起こっ
ている現象に気づき、その現象別に英文法をとらえて各単元別に正確に知識を運用するこ
と”なのである。そう、現象に気づくことがカギとなるのだ。英文を読む中で発生している
"現象"に合わせて、解いていかなければならない。富田先生の言葉を借りるなら、"あなたは
試験場に1人で行き、二つのまなこで見えたものしか処理できない"。
だから英文解釈(構文)、すなわち"現象別の"英文法が大切であり、英語ができる上での肝
になるのだ。まぁそれでもピンとなっていない人もいるだろう。代表的な例を挙げるなら、
"倒置の可能性"、"代名詞の処理手順"、"準動詞の意味上のSの原則と例外、書き方"、"that
節の全体像と判別法"、"as 節の全体像と判別法"、、、と言ったものである。こういった現象
にどう処理していくのかを勉強する。
ちなみに、もともと富田先生の”一学期の”授業は、この"現象別の"英文法をメインに展開し、”単元別”の英文法は単科の付録で補う形で行われていた。だからちょうど授業とテキストの
付録が補完し合う関係であった。
そう、この本はその両方を兼ね備えているので効果が絶大なのだ。ただそれぞれの場所がど
れなのか、初めて富田英語をやる人には難しいところがある。というより所々に登場してく
るので、そこをピンポイントでやるのは大変である。もちろん通しでやるのが一番いいのだ
が、本来は現象別の解説→単元別の解説である。そこでまずは ⭐をつけた章を見て、現象
の全体像を掴んで欲しい。そこからそれ以外の部分をして、単元別に学習すると効果がある
と思われる。
⭐をつけた章は富田の英文法の三本柱、文型・時制と法・同じ形の反復について徹底的に
解説しているので、まずはここから見て欲しい。柱を作るためにはまず土台構築をし、そこ
から上に作るものだ。同じように現象の土台を理解し、単元別にやって積み上げていく。そ
うするとやがて完成に近づき、それぞれの柱を扱えるようになる。
特に言っておきたいのは、富田先生の授業の代名詞といってもいい"文型"を理解するために
は、しっかりとした勉強をしなければいけない。それがVについてである。
英語の勉強がある程度進んでいる人ならご承知の通り、Vには必ず文型があり、文型ごとに
意味があることを知っているはずだ。そして富田先生はよく授業で「文型をやることで、V
の意味を決められ、句と節の働きも決めることができる」と何度も説くのである。それだけ
文型には意味があるのだ。
ただそれには、それぞれのVが持ち合わせる文型と意味については知っておかなければな
らない。もちろん全部ではないものの、基礎的なVについては知らないといけないのだ。
それが"V"についての英単語学習である。これは富田先生が私塾サイト経由で売っている
verbs という参考書があるので、それをぜひ活用しながらやって欲しい。
そして、個人的に大好きなポイントは◆のところである。突然だが、英語は日本語とは全
く違う、というのは間違いないだろう。ところがある部分で共通するところがある。もちろ
ん「言語である」こともあるが、それ以上に大事なのは"論理"である。"論理"は思考などを
進めてゆく筋道そのものを指す言葉であり、要は繋がりを示すものなのである。これはどの
言語にも使える非常に大切な関係であり、これをベースに文法を解説したり、読解していっ
たりする。だからこそ、ここはぜひマスターして使い慣れるようにしてほしい。
というわけで星は無限、、、と言いたいところだが5個までが限界なようなので妥協しよう。
そしてこれをもって富田先生の”読む・解く・書く”参考書がそろったことになる。改めて全
体を見通してみよう。
英単語 とみ単、verbs
単元別&現象別英文法 思考する英文法・富田の入試英文法ver1
構文(実践演習) 富田の英文読解 100 の原則・基礎から学ぶビジュアル英文読解 基本ル
ール編・構文把握編
解法紹介&演習(長文読解) 富田の英語長文問題 解法のルール 144・富田の入試英文法
ver2(整序問題)・ver3(会話問題)・ver4(正誤問題)
英作文 富田の英作文 99の例文から
これで富田先生が何かの間違いによって旅立たれても問題がない状態になってしまった
(本心ではないですよ、念を強く推して言っておきますが)が、”代ゼミの鉄人”としてこれ
からもずっと活躍してほしいものである。
なお、富田先生の授業を受ける人向けにひとこと。この”思考する英文法”の登場によって、
どの授業でもやることが統一されることになる。それは”この本の内容を一学期中に頭に入
れること”だ。
富田先生の通年の単科ゼミにおいては一年間の流れというものがあり、
一学期 知識(=単語、文法、論理)
夏&二学期 観察力(=設問別解答力育成)
冬
判断力(=合格点をとる考え方)
の流れで進んでいく。この流れに沿って考えると、知識をやることになる。実際、一学期の
授業の始めでは「一学期で大切なのは、授業以上に付録にある文法知識を頭の中に入れても
らうことです」と本人が言うぐらいであり、その付録の量もかなりの厚さが”あった”。そう、
それはもはや過去のことになるのだ。付録では200Pだったのが、500Pの大進化をとげた。
当然、より一層過酷なものになる。
加えて富田先生について行く上で大切な"verbs"という、富田先生運営の私塾のサイト経由
のみで手に入る、各動詞のとる文型とその意味について書いた参考書を同時進行でやる必
要もあるのだ。
まぁはっきり言って”地獄の修行”になるのは間違いないが、その分得るのは”絶大で裏切ら
ない英語力”であることは約束しよう。そこは初めにもかいた三つの⭐のモットーにもあげ
た。
だが、ここまで読んだ”まともな”人なら「富田先生の”一学期の”授業は、この"現象別の"英
文法をメインに展開しているんだから授業の価値は?」と思っただろう(思えない人、そも
そもちゃんと読めてますか?)。
そこでこんなことを考えてみよう。”思考する英文法”は巨大な宮殿のようになっている、と。
巨大な宮殿は、もちろん部屋ごとに統一的な記号番号が振られ、その部屋ごとに詳しい説明
がある。宮殿内の地図(本では「目次」がそれにあたる)に従い、順番に順路を回ることで、
それぞれの部屋の内容は理解できる。一方、巨大な宮殿にはガイドツアーがつきもの。ガイ
ドツアーは宮殿内の主要な部屋を選んで限られた時間内に見て回るが、”優れた”ガイドツア
ーであれば、ツアーを終えたときには宮殿の全体像が明確に見えるようになっており、その
後一人で各部屋を鑑賞していくと、理解が一層深まるものなのだ。
つまり、思考する英文法と”一学期の”授業の関係は、宮殿とガイドツアーの関係みたいなも
のである。宮殿を一人で周り尽くすもよし、ガイドの手助けを借りて全体像を把握し、その
後必要に応じて必要な部屋を回るもよし、という選択式になったのだ。だから一人で学習す
るのもいいが、”超絶優秀な”ガイドツアーこと富田一彦先生についていったほうが全体像は
掴みやすいことは言っておく。(なおこの渾身のたとえ話は富田先生よりである。え?自分
で思いついたんじゃないのかって?そんなことできるならこのレビューなんか書いてない)
あとこれはあくまで”一学期”の話であり、夏季講習以降の授業と付録の関係は全く違ったも
のになるのでお楽しみに。
$$$2025 年4月20日追記$$$
初版発刊から1週間経とうとしている現時点で、この"思考する英文法"は多くの人に影響を
及ぼしている。その中で多くのレビューが見受けられたが、使い方やレベルの立ち位置の点
についての声がかなりあったので、そこを追加して書き足しておきたい(自分としても、こ
こまで書いておきながらまだ書き足りないと思っていることに驚いている。やはり富田先
生の力は計り知れない)。
主に追記したい点は三つあり、
・この本を使う前提の土台
・富田英語を適用する範囲
・目指す視点の先
である。順に行こう。
・この本を使う前提の土台
「そもそも富田の英語ってどれくらいのレベルを要求しているの?」という質問、これは非
常にごもっともである。
よく聞くのは「初学者には向かないよね」ということだ。これは実際その通りで、ある程度
の英語の基礎知識は前提となっている。ただ、実際問題として、どこら辺までいるのだろう
か?富田先生についていくためにはどんなことをすべきか、自分なりに考えてみたので載
せてみる。
前提として、英語学習の勉強は試験勉強(主に大学受験)にむけてやるとして考えるものと
し、アルファベットはできるが、それ以外は0からやるとする。そうなると全体像は次のよ
うになる。
⓪基礎英単語の一語一訳
①中学英文法
②"単元別の"英文法
③"現象別の"英文法+英単語学習
④長文and英作文
②と③の話はし尽くしたので⓪と①について詳しく話そう(④は後ほど)。
⓪基礎英単語の一語一訳
まぁやはり英単語はある程度知らなければ話にならない。ただ初期段階では、多義語であっ
ても一つの単語で多くのことを覚えるのは非効率であると考えます。そこでまずは"赤字訳
と品詞を一語一訳一秒で"をモットーにしてゴリゴリ英単語を覚えるべきと考えます。
そもそも"一語一訳"を"一秒"で瞬時に出し、"品詞"も加えて覚える時点で相当なストレスが
かかるのは間違いないのでこれぐらいがいいと思います。で、問題はどこまでが"基礎"単語
なのかについてですが、今回は富田先生を前提に考えるとターゲット1900orシス単無印ま
でだと考える。だから本当にゼロからなら
ターゲット中学→ターゲット1200or1400→ターゲット1900
あるいは
シス単中学→シス単basic→シス単無印
と言った感じで3冊ぐらいはこなすべきと考えるので、この段階でダブりがあっても5000
語ぐらいは覚えなければならないのだ。
ある程度英語が得意ならともかく、初学者や英語嫌いな人にとってはまずここが鬼門です
から死ぬ気で頑張って欲しい。正直ここを突破しないことには先はないので。
①中学英文法
ここは⓪と同時並行してやってもいい。まぁこの段階の話は③に行くと無価値になるので、
やる意味あるのか?とある程度やれる人以上は思いがち(というか、思えない人は③の話を
聞いてないだろう。ニワトリじゃあるまいし)なのですが、実際にはこの段階で出てくる英
文法用語には慣れて置かないと、後々厳しくなる。要は文法用語が出てきた時にアレルギー
が起きないように対策を仕掛けると同時に、それぞれの文法単元のある程度のニュアンス
は掴んでおいてほしいから設けている段階。
一言言っておくと、中学英文法の問題点は"正しいと不正確が混在し、知識がバラバラであ
る"ということだ。特に中学英語でやる話は、表現暗記が重視されるので文法ルール上で扱
う意識を持ってやることがほとんどない。だから"不正確"な知識になってしまう。かと言っ
て"三人称単数には一般動詞にsをつける"といった"正しい"知識もあるため、両方の知識が
混在していて扱いがしにくい面がある。まぁそもそも論として文型を使わずに英語を読む
こと自体ナンセンス、という話なのだが中学程度で出てくる用語がわからないのはまずい
ことになる。用語が何を指すかわかるものが少ないと話が進まなくなるので、あくまでその
ために設定している段階ということをお忘れなく。
そして②をやるわけだが、まぁここら辺あたりまでやっていれば"思考する英文法"にはつい
ていけるとは思う。そもそも②と③を組み合わせた本なのである程度のものが求められる
のは当然である。勉強をしていて、②までをやってきた状態ならバッチリであろう。さてそ
こで次の話をしよう。
・富田英語を適用する範囲
ここまではあくまでこの本を"使える"前提の話をしてきたが、"使う"前提もまたある。それ
は富田英語をメインにするか、それ以外かである。
前者なら話は簡単である。この"思考する英文法"を徹底的にやることだ。そしてここまで言
ってきたように、この段階は一学期が終わるまで(七月前半)に終えて欲しいのだ。
しっかり"現象別の"英文法(何度目のご登場だろうか)をマスターし、ちゃんとした"英単語
学習"(V に関することはもちろんのこと、他の品詞の単語も核となる意味や文法的知識も
覚えること)をやり遂げたものが先ほどの④に(つまり夏期講習以降の話に)進めるのだ。
この段階では、"本文の内容は時間をかければしっかり理解できる"ところから出発する。こ
こからは試験本番の問題で求められるものについて考えながら勉強していくことになる。
実際、試験では「この本文を全訳せよ」なんて問題はそうそうない。あっても下線部和訳が
限界だろう。
そこで設問別に解法を考えながら、問題に対する考え方を身につけるのがこの段階でのメ
インである。和訳はもちろんのこと、空欄補充や内容一致、説明問題、整序、正誤問題など
の設問別に。そしてその解法を沢山の問題を解きこなしながら話を進めていくことで、段々
と問題が解けるようになっていくようにしていく。これでやっていくことになる。
さて、問題は後者なのである。ただ実際には"構文で有名な先生だから、構文を担当して欲
しい"感覚の人も大勢いるだろう。つまり③を富田の英語でやって、他の話は他の講師に任
せる人。だがその人達は、おそらくメインの講師が他にいることになる。そうすると、富田
の英語を他の講師の英語に"完全に"合わせるのは中々むずかしくなる。
例えば"Oの欠けたto Vはふつうではない"というのをみた時、この話がしっかり理解でき
るだろうか?「ふつうではないってなんだ?」「そもそもOの欠けたto Vって何?」って
なる人がほとんどではないだろうか(ちなみに理解できる人、Oの欠けたVingと言われた
ら列挙できるだろうか?できる人、あなたは立派な富田信者だ)。まぁ正直、こうなってし
まう人がこの本を使うのには向かないかもしれない。
ただこういうのは"あだ名"をつけるみたいなもので、そのあだ名は人によって異なるのは間
違いない。そこで、オススメの使い方は"辞書として使う"ことである。"現象別の英文法"の
見方をつけ、気になる単元を読んでいくのがやりやすい使い方だろう。ただし、間違っては
いけないのは、"学問的厳密さ"や"表現網羅性"を追求するものではないことに注意してほし
い。
最初に言ったように、英語の本質は英文法につきる。ただしここでは"学問として"英文法を
追求するのではないのだ。"語学として"英文法を学習し、それをうまくやってくださったの
が富田の英語なのである。いや、英文法にも例外は存在する。でも、まず8、9割に通用す
るルールから学んだ方が、多くのことに対処できるようになるのでそこから処理していく
のが合理的であろう。実際に使える英語として学習するもの、それが富田の英語なのだ。
"学問的厳密さ"や"表現網羅性"を追求した参考書ならそれこそ腐るほどある。ただそうゆう
ものを求めている人には向かないなのだ。
まぁなんにせよ、両者に言えることは"俯瞰した視点で英語を捉え、各単元を制覇する"発想
で挑んで欲しいことである。
なお、沢山のレビューをみていて感じたこととして「単語の解説が詳しくない」「実践の英
文解釈として向かない」などの話が見受けられたが、正直言ってこれはナンセンスと感じた。
まぁ最近の参考書は丁寧なものも多く、単語や文法、構文がオールラウンダーで乗っている
ものが増えてきているから、そうして欲しいという意図なのだろう。ただ、こういう発想で
富田先生の参考書を使うつもりならはっきり言って他を当たって欲しい。
よく富田先生の参考書は名著だと言われる。その理由は極めてわかりやすい。"一冊一冊に
つき、各テーマを徹底的に話し尽くす"からだ。この"徹底的に"があるから、名著たる所以な
のだ。
オールラウンダーに乗せていく参考書は、知識が増えるけどまとめられることがないから
結局全体像が見えないのだ(まぁあっても表にまとめるぐらいだろうか。でもそれって"ま
とめ"というより「集め直した」だけでは、、、?)。そうなると、自力でやっていく術がない
ことになる。そういう参考書の類に言えることは"出し惜しみ感が垣間見える"ということで
ある。
だが、富田先生はそんなことをしない。"単語なら単語、VならV、解法なら解法のテーマ
を徹底的に"と言った感じで、それぞれを真っ向からいざ真剣勝負といって解説してくださ
るのだ。だから一冊一冊が力作となり、名著になるのだ。まぁ、ただ純粋にそれぞれのテー
マごとを知りたくて、先ほどのレビューが出たとしたら(まぁ富田本の全体像が見えていな
いのは、ちとストライクゾーンが狭いと感じなくもないが)その本達を紹介しよう(まぁ前
に書いたものを乗せ直すだけだが。え?手抜きだって?ならここまでスライドしておいて
また戻ってくれるんですか?どうせ手間がかかってやらずに放置するのが目に見える)。
英単語 とみ単、verbs
(とみ単は単語の解説が非常に詳しいのでオススメしたい。ただし第 3 部の××シリーズ
については気になったら使う程度でやることをすすめる)
単元別&現象別英文法 思考する英文法・富田の入試英文法ver1
(ここはお腹いっぱいだろうから割愛)
構文(実践演習) 富田の英文読解 100 の原則・基礎から学ぶビジュアル英文読解 基本ル
ール編・構文把握編
(実際の構文読解を実践するならここあたりの本でやって欲しい。100の原則をやって、構
文把握編をやるとかなりの量が演習できる)
解法紹介&演習(長文読解) 富田の英語長文問題 解法のルール 144・富田の入試英文法
ver2(整序問題)・ver3(会話問題)・ver4(正誤問題)
(それぞれの解法が革命的であるのでしっかり理解して身につけるとかなり解答力が飛躍
するのでオススメしたい。演習量が欲しいなら過去問も併用してやってみることもすすめ
る)
英作文 富田の英作文 99の例文から
(実はこの本もレビューしているので、そっちにいって読んでもらいたい。え?何故ここで
書かないのかって?ならここまでのレビューの分量をもう一回読むことになりますけど、
そんな心の余裕はありますか?)
・目指す先の視点
さて、何故この"目指す先の視点"という項目を作ったのか。
突然だが、この"思考する英文法"では明確に語られていることがある。それは抽象化能力に
ついてである。この話を通じて得て欲しい発想が、"富田の英語を通じて頭を良くして欲し
い"ということである。
富田先生は代ゼミで長年、東大英語を担当されている。そして多くの東大受験生を合格させ、
支持されてきているわけなのだ。さてそれは何故なのだろうか?そもそも東大英語を解い
て解説をするならどの英語講師にもできるはずなのに、何故富田先生が支持されてあるの
だろう?それは"科目の垣根を超えた大事な視点を与えているから"だと考える。
言ってみれば英語なんて、受験からすれば一つの科目でしかない。その一科目の「知識」を
与えるだけなら誰でもできる。だがその科目の"壁"を超えた視点を提供するのは中々できる
ものじゃない。
「え?それっぽいかっこいい言葉を言ってやることぐらいできるだろ」って?そう、できる
のだ。では問おう。"その発言の筋を通して科目を教えることはできるか?"と。これができ
る人は多くないのだ。英語なんて、まさにその典型と言えるだろう。「前から読んで」とい
う英語講師は世の中にごまんといるのだ。だが、その発言を実行する人間はそんなにいるの
だろうか?例えばそんなことを言う講師がthat節を教える時に「いいですか?that節の後
ろが不完全なら関係代名詞、完全なら接続詞ですからね。後ろによって決まるんですよね。
だから気をつけましょう」って言って説明を終えたら、はっきり言って受講するのを辞める
だろう(学校の教師だったらどうするんだって?まぁこっそり内職でもしたらどうです
か?もちろん自己責任だけど)。だってこれだとthat節の後ろを見ないと判断できないんだ
から、後ろを見て先に決めれば判断ミスをしなくて済む、、、けど前から読めないじゃん、っ
てなって自滅することになるからだ。せめて「パターンが決まっているからこの表現を覚え
てね。そうしたら前から読めるからね」って教えてくれる方がまだ筋が通っている。
だがここまで話してきたように、表現を覚えていくのは結果的には知識の丸暗記で終わっ
てしまうのだ。そんなことは富田の英語では求められていないのだ。抽象化して普遍的なも
のにしていく姿勢、そのものを大切にして欲しいのだ。だから富田先生の姿勢は"全体を見
る"のであり、英文法を巧みに操っていくのだ。そしてこれは崩れることなく、一貫して保
たれているのだ。説得力がまるで違う。
だから抽象化をしていく姿勢で挑み続け、そうすると頭が鍛えられていく。
そして、ここからが大切なのだ。目指す先の視点は"富田の英語を超えるものを出す"ことだ。
天井を決めてしまっては、それ以上になることはできない。ただその天井を破るためには、
その天井を知り、極め、その上で新たな視点を見抜いて破っていく必要があるのだ。個人的
には富田先生の教える英語は"みんなが教えられる英語教育の究極形のもの"だと考えてい
る。見方がちゃんとあれば、富田の英語は見えてくる。だから本来はみんなが富田の英語を
身につけていてもおかしくないはずなのだ。
それがどういうわけか、よく訳のわからない教育に引っ張られて表現を丸暗記して、理解が
できずして滅んでいく者達が多くいる。だからまずは土台を身につけるのだ。そして、そこ
からが"本題"なのだ。富田の英語をこえる理論が築き上げられるか、新たなる視点を作り上
げられるか、、、。そうやって何かを超えるものを追求していく姿勢になっていくことが"目指
す先"なのだ。
ということで、この私なりのガイドも参考にしながらぜひ頑張って取り組んでいただきた
い。
$$$長き追記終了$$$
(^◇^;)2025 年5月12日増量追記(^◇^;)
GWが終わり、出版から一ヶ月が経とうとしている。以前より多くの人に行き届き、以前よ
り更なる感想が飛び交ってきた。そんな最中、この本の誤植に気付いた偉い人が登場した
(これは富田先生から一緒にご飯を食べに行く権利を発行されるに違いない)。それだけ鋭
い観察力を持って、この本に挑んで行く気力は持ち合わせておきたいものである。
GWというのは爆弾が潜んでいるものである。なにしろ"五月病"という非常に恐ろしい悪魔
が密かに精神を蝕み、堕落へと誘われてしまう。まぁ世間のほとんどの人間がこの症状に見
舞われており、阿鼻叫喚の嵐がでることは毎度のことである。だが受験生や勉強している
人々にとってはそれどころではない。特に、急流を流れ下りつつ、やがて最後に現れる致命
的な滝に達するまでになんとか陸に上がらなければいけないというミッションを抱える受
験生には、黄昏れている余裕自体がない。「やる気が出ない」というのなら、才能がないの
だからやめたらいいのだ。最もいけないのは、そういう自分の虚無感を周りにまで蔓延させ
ること。君がどうなろうと君の勝手だが、周囲を巻き込まないように(まぁ学力向上はいつ
だって自分との闘いである、ということは百も承知だろうから全ての行動は自分のために
なるようにして欲しい。もちろん他人には邪魔をしないように)。
こんな厳しめの言葉も思いつつ、頑張って欲しいものである。さて、一ヶ月も経つと色々な
本が出版されてくるものであり、それを受けてまた騒ぎ出す(騒ぎたがり、の間違いか?)
人々が登場してきている。懲りずに目も当てられないレビュー(つまり聞くに値しない妄言)
が増えてきており、「こんなバカなことするなら勉強すればいいのに」と思うものである。
しかしながらこの影響でまたまた書きたいことが出てきたので更なる追記をしようという
ことになった(何処まで増えるかはもはや予測不可能である)。
さて今回のお品書きは以下の通りで、
・学習者全てに向けて
・日本語を学ぶ大切さ
・高き壁、リスニング
である。それでは順番にお出ししよう。
・学習者全てに向けて
最近、有名な英語講師の分厚い英文法の参考書が登場してきている。そしてまず大前提とし
てこのことは非常にありがたいことである、ということはしっかり認識して欲しい。もちろ
ん多くの人は「そりゃ、有名な先生の本が世に出る事によって更なる広まりがあるからだろ」
と思っているだろう。それは、そう。まぁ多くの予備校講師は、教室の生徒に向かって講義
しているんだからその内容を外に向けて出すということはあまりない(まぁネットやサテ
ライトで講義している、というのもありうるがそれだって受けられる対象者は限られてく
るものだろう)。その意味においても本で学習できる事に意味があるだろう。だが、そんな
ことが思えるのは大前提の根幹をなす"重大な意味"があるからだ。それは"文字で内容が書
かれてある"ということである。
「は?そんなの当たり前だろ?」という顔が容易に想像がつく。だが問題なのは、そう思っ
ている多くの人はそのままで感想が終わってしまうことである。
そもそも当たり前ということは"否定しようがない事実"なのである。そこから考えていけば
思いつくことがいくらでもあるのに、それを無視してつまづく事は”マヌケ”そのものである。
だからまずその態度を改めるべきだ。
そして今回の三つの話、正直言ってこの話が肝であるのだ。その"当たり前"が、どれだけ重
要な意味を為すかというのを理解出来るかがキーになる。だからこそしっかりとした態度
で読んでいただきたい。
話を元に戻そう。文字で書いていること、この話がどれほど重要なのかはすでに我々は知っ
ているはずだ。え?いつそんなことやったのかって?それは"歴史"である。そもそもなぜ
我々は実際に見たことはおろか、聞いたことも感じたこともない歴史の話が勉強できるの
だろうか?それは文字で書かれた文献資料が残っているからである。義務教育という名の
お遊びメドレー期間を駆け巡った人(つまり小中学生のわんぱくな時期に遊びまくった極
めて当たり前の健全な人々)ならご承知であろう、歴史は旧石器時代、縄文時代、弥生時代、
古墳時代、、、と歴史が続いていき、今の令和時代に繋がるという話、これができるのは文献
資料のおかげであるのだ。文字で書かれた情報はその資料がなくならない限りずっと残り
続けるものであり、これは非常に有効なものであるのだ。
これは言語でも同じことが言える。本はもちろん、文字で書かれたすべてのものには何かの
言語で書かれている。その文字情報があれば、どんな内容であったのかを残し続けられるこ
とができるのだ。そして、読み方さえわかればいつ何処で誰が見ても確実に理解出来るから
だ。そのために生み出されたのが”文法”である。
そもそも文法ができたのは、言語が文法というルールに基づいて構成されるため、そのルー
ルを体系化し、より正確に理解し、そして各言語の文章を作成するために必要になったから
だ。
英語は、単語の意味だけでなく、それらの単語をどのように並べるか、どのような文法的な
構造を持つかによって意味が大きく変わる。そのため、文法を学ぶことで、英語の文章をよ
り正確に理解し、また、正確に英語で表現できるようになるのだ。
歴史的な背景を考えてみれば、英語はゲルマン語族に起源を持つ言語だが、ラテン語、フラ
ンス語など、様々な言語の影響を受けながら発展してきた。英語の文法を体系化したのは英
国の文法学者たちであり、彼らは規範文法(よくいわれる学校文法のこと)を確立した。英
文法の体系は、そうやって多くの研究者や文法家によって長い時間をかけて発展してきた
ものということだ。そのおかげで日本はもちろん、英語を学ぶどの国の人でも、英
語学習において英文法が重要な役割を果たすようになったのだ。
だからこそ、「英語は音声言語である。それを忘れて紙の上で論理をこねくり回し、英語を
理解した気で酔っている。」だの「日本人のための英文法書」といった”支離滅裂”なレビュ
ーなんぞは意味をなさないため、捨ててしまえるのだ(以上証明終わり、Q.E.D.である。こ
んな発想にさせてしまった講師がいるとしたら、それはぜひとも完膚なきまでに問い詰め
ていきたいものである)。
ちなみにこの前者の”とんちんかん”レビューは、後の”高い壁、リスニング”でも徹底的に叩
き潰すが、この類の質問が出てきてしまう理由として規範文法と記述文法の存在があるの
だ。
規範文法と記述文法は、言語学における文法の二つの視点だ。規範文法(prescriptive
grammar という)は、あるべき言語の姿(標準語など)を規定し、正誤を判断する文法であ
る。まぁ”あるべき姿”を規定する文法で、文法や表現の正しさを重視するということだ。こ
れが学校で学ぶ文法規則など、標準語の規則がこれにあたる。
一方、記述文法(こっちはdescriptive grammar)は、言語が実際にどのように使われてい
るかを記述し、その構造や変化を分析する文法だ。つまり「ありのままの姿」を記述する文
法で、言語の実際の使用パターンを分析し、その構造や変化を説明するものである。
こう聞くと「なんか記述文法ってすごそうじゃない?」と思えるだろうが、それが行き過ぎ
た結果として先ほどのレビューが生まれたのである。
例を挙げてみよう。オムレツを作って下さいと言われた時、本当の初心者であるならば、ま
ずはレシピを見て決められた手順通りに作っていくだろう。ちゃんとそこに書かれている
バターと卵を用意して、フライパンの火の入れ方も含めてちゃんと手順通りにやっていく
でしょう。そうしてシンプルな卵のオムレツが完成ということだ。これが言ってみれば規範
文法ということだ。
ところがある程度料理ができてくるとその作り方は 1 つではありません。例えばシンプル
な卵だけのオムレツがレシピに書かれている事はいくらでもあり得るでしょうが、そこに
アクセントとして野菜を入れてみたり、お肉を加えたみたいなどしてみると、おいしいもの
も出来上がるでしょう。そうして自由自在にいろんなものを作っていくものであり、人それ
ぞれのオリジナルで作っていくもの、それが記述文法ということです。
で、こう言ってみるとわかると思うのですが、そもそも記述文法の話を議論するためには、
ちゃんとオムレツが作れることが前提にあるわけです。つまり記述文法だけが大切だ、と言
ってしまう人は適当なことをやって出来上がったものをオリジナルだと言い張って”混沌と
したものを認めてしまう”ことになり、その態度に問題があると言うことです。こんなこと
自体、多くの先人たちが、時間や労力や脳をしっかりとかけて培ってきたものの意義を丸つ
ぶししてしまうわけです。だから記述文法が大切(言ってみれば話し言葉や音声言語が大切
と言ってしまう)というその態度は非常に致命傷であると言うことです。
ところが反対に、では規範文法だけでいいのかと言われればそうではありません。もちろん
卵だけのオムレツも美味しくて、シンプルだから、これでもいいと言う人はいるでしょう。
しかしそうしてしまうと、それ以外の発想が出てこないことになります。それは言ってみれ
ば、発想が固定されたと言っても過言ではありません。それはまわりまわって支配されるこ
とになって、思考できなくなってしまうわけだ。だから規範文法から出発して、その後に記
述文法の範囲で実際の運用の場所を見ていくと言う態度が大切なのです。
そう、結局は両立すると言うことが大切だ。皆さんは、よく0か100かで物事を考えよう
としてしまう癖がある。まぁ今言ったような規範文法と記述文法と言う 2 つの文法がある
よ、と言った時にじゃあどっちがいいんだ?と言うふうに論争を起こしかねないこともそ
うだろう。しかし言ってみればその議題自体が間抜けであると言うことである。
そして富田先生はずっと8、9割に通用するルールを覚え、そこから残りの1、2割を対処
していこうと言っている。言い換えてみれば、8、9 割は規範文法の話で済むわけだ。とこ
ろがもちろんそれだけで全部が語れるわけではない。実際の運用場面に出てくると、1、2
割は記述文法の範囲でやっていくのが良いと言う場面もあるのだ。だから両立してやって
いくと言うのが大切なのである。
さて、ここまで”文字で書かれていると言うことがどれほど大切なのか”と言う話をしてきた。
しかしこの話をしてあることに気づけていない人は、まぁかなり抜けていると言わざるを
得ない。そしてこれは多くのレビューはおろか、昔からある程度根付いてしまっている話に
も言えることである。それは”ネイティブらしくないと言う話や日本人のための”といった”
意味不明な”話のことである。そこで次の話に移ろう。
・日本語を学ぶ大切さ
さて、先程の後者の話である「日本人のための英文法」と言う”わけのわからない”話につい
て徹底的に話そう。ただこの話は、1番最初にあげた的外れな質問に対する切り込みを展開
したものになるので、そこのところはご承知いただきたいと言う事は先に述べておく。
なぜか日本人が英文法を教えると、「それは日本人向けの英文法であって、ネイティブらし
くない」と言うわけのわからない話が出てくるのだが、こういうことを言う人に私は聞きた
いんですよ。例えばアラブ人が英文法を教えたら、それはアラブ人のための英文法と言うん
ですか?中国人が英文法を習ったら、それは中国人のための英文法と言うのですか?と。そ
んな具合にして訳のわからない「XXのための英文法」という意味不明なものが続出してし
まう、そういう間抜けなことを言っている人たちに耳を傾けようとすること自体、言ってみ
れば馬鹿だと言うことだ。
英文法は変わらず英文法であるのだ。だから誰が教えようが、どの国の人か教えようが、そ
れは変わらないということが大切なのだ。そんな話す必要もないであろう前提ですが、話さ
なければいけないと言う悲しい現状を踏まえ、この議題に踏み込みます。さて、まず我々や
日本人であると言う前提があるんですが、この話はある前提が抜けがちであり、それを踏ま
えた上で考えるべきだ。
その前提とは、"我々はあくまで日本に住む日本語を使う日本人であり、英語はただの外国
語として扱うべき"ということである。そう、我々日本人は母語として日本語を扱っている
のだ。日本語は論理性が高い言語であるが故に論文を書いたり、高度な学習内容を日本語で
勉強できるわけである。その意味においては、英語が"絶対"必要というわけではないのだ。
まず念頭に置かなければいけないのは日本語力の向上である。
しかし現実では小学校からの英語早期教育が始まり、ろくに日本語が操れるかおよそ怪し
いにも関わらず英語までやろうというのだ。その結果として、英語が得意な生徒が増えるど
ころか苦手な生徒が続発し、国語すらも怪しくある生徒が増えている、、、のだから笑止千万
だ。個人的に、英語早期教育のせいで日本語もできなくなる人が増えて、その人がそのまま
社会に流れ込んでどうにもできなくなる社会に凋落してしまわないか、内心怯えている。
まぁこれは子供の例だからピンとこないかもしれないが、大人だってそうだ。
え?なんでって?さっき私は"日本に住む"と書いた。そう、その意味においても英語が"絶
対"必要というわけではないのだ。
あっそうそう、最初に断っておくが言語学習において語彙から逃げられないのは百も承知
である。結局は語彙は必要なのであり、辞書も必要なのである。これに否定する気は毛頭も
ない。ただし、これこそが抜けがちな盲点なのだ。
例を挙げよう。あるYoutube チャンネルで、ある講師の教え子がロンドンから留学して帰
ってきて、講師に「英語は9割が語彙力」と言ったという話があった。
この話、一見正しそうではある。でもこの話、前提として生徒は「ロンドン」に行っていた
のである。ともすれば英語は"絶対"(といっても今は翻訳機能があるからなんとかなるだろ
うけど)必要な環境であったのは間違いないだろう。
ハーバード大学とGoogleの研究者たちによって行われたある調査によると、英単語の合計
は102 万2千語にも上り、毎年さらに数千語ずつ増加しているだろうと考えられている。
それだけの英単語を覚える必要がある学習は、そういった英語が"絶対"必要な人に向けたも
のなのだ。そりゃ留学とか移住する人、英語関係の仕事をしている人にとってはそれこそ"
絶対"必要だろう。
でもちょっと待って。本当にあなたはここの人に属するのですか?本気でその方面に向か
う人なのですか?
この答えがNOであるなら、まずそもそもとして102万2千語もの英単語を覚えさせる学
習法を提供しようとする講師は間違ってます。おそらく試験で使うから、論文とかを書くか
ら、という人が多いはず。その意味において「ネイティブらしくない」、その批判は間違っ
てる。我々は日本人で、外国語として英語をやるなら、まず原理・原則からマスターすべき
なのである。そうして8,9 割使えるルールを身につけた上で残りの1 割ちょいを処理すれ
ばいいだけなのだ。ともすれば覚える単語数はせいぜい 2 万語、なんならこれでも多すぎ
るぐらいだろう。
それからさっきの質問にYESと解答した人、じゃぁ聞きますけどね、「英語の本質がわから
ない」とか言った時、じゃあ"英語の本質って何?"っていう質問に答えられます?まさか、
アメリカの赤ん坊みたいに、10 年もかけてひたすら英語の作品とか本を読んだり聞いたり
して「なんとなく」を身につけていく事が「英語の本質」だと思っているんですか?もし本
気でそう思っているなら、少なくとも大学には行かない方がいいでしょう。だって演繹的に
やってなんとかなる、と思っている人が、演繹的なものから普遍的なルールを導き出すこと
に力を入れる大学という場所に向くわけないじゃないですか。だからその意味でも「英語の
本質がわからない」という批判も間違いです。
ということで、まぁもうここまで話してきて英語の本質をわざわざ話す必要は無いと思う
が(というかわかってない人、タコですかあなた?)この”思考する英文法”を通じて日本語に
も通用する発想がある。
⭐主語と述語(SP)の関係
⭐修飾語(M)のかけ方
⭐漢字(まぁ語彙の知識も含めて、かな)
まずSP の関係は英語では第5文型の話で出てくるのがまず最初だろう。SVOCがあって
OとCの間には、SPの関係があると言うのは、もう今更語る必要がない(と思いたい)。
しかしこれは英語に限らず日本語もそうです。日本語だって、「私は兄がいる学校に行った。」
と言う文を見たときに「私は」と言うS、「行った」と言うP、この2つの関係がまずある
と言うこと。だからまずは主語述語をつなげていくと言う発想が非常に大切。
そして英語では修飾語のことをMと言い、そのMのかけ方も非常に学ぶべき姿勢だ。日本
語の場合は修飾語と、修飾語をかける先の被修飾語といった2つの関係がある。そしてその
修飾語と被修飾語の関係をちゃんと考えていくと、日本語を読むときに”なるほどそういう
説明をしているのか!”と言うふうになっていくわけです。
さっきの例で考えると、「兄がいる」という修飾語が「学校に」という被修飾語にかけてあ
るという関係が理解できるだろう。だからちゃんとそこも見抜いていかなければならない。
そして最後に漢字とはどういうことかと言うと、まぁ漢字を皆さん見たときに「漢字は漢字
だよ」と言う人が多い。が、そう言えてしまうのは漢字の意味を無意識に覚えているからだ。
で、問題はその意味はどうやって認識しているのかというのは話だ。
突然だが、漢字には訓読みと音読みがある。おそらく普段は音読みで漢字を読んでいること
が多いだろう。しかし音読みと言うのはもともと漢字を発祥とした中国のものであって、そ
れは日本発祥ではありません。訓読みが日本発祥である。そして、日本人は訓読みで見れば
あらゆる漢字も理解することができるのだ。だからそういったふうにまず漢字は訓読みが
できるかどうか、そこが大切です。そしてまぁ漢字に限った話ではありませんが、いわゆる
日本人とかがある程度知っておくべき現代用語の基礎知識といったような用語はしっかり
と覚えておくべきでしょう。
というわけで、ここまでは英語をしっかり読み書けるようにする話を徹底的にしてきたわ
けだ。ところが実はある禁断の領域を話していないことに皆さんは気づいているだろうか
(と言いつつ、気づいている人はかなりいると私は思っている)。その禁断の果実について話
していこう。それがリスニングについてだ。
・高き壁、リスニング
ここまでで、"読み書く"という段階は一区切りついた。それではリスニングについて考えて
みよう。
ここから厄介なのが、三つの壁が登場する。話し言葉、発音、伸びのスロースターターであ
る。
突然だが、世間の「受験英語は話せないから役に立たない」批判はよく聞くだろう。で、こ
んな批判に"大学で求める英語力と、世間が求める(幻想を抱いている、の間違いかもしれ
ないが)英語力は全く違うんだ"という"正論"を返そうものなら更なるクレームが来るのは
容易に予想できる。
え?なぜこれが正論なのかって?それではみなさん、思考実験してみましょうか。例えばあ
と 1 週間後にアメリカ人に日本旅行のツアーガイドをやってくれ、なんて頼まれたとしよ
う(なんとまぁ、過酷であろうか)。さて、あなたが英語をまともに扱えないとしたら何を
して対策しますか?おそらく、あなたがやるのはほぼ間違いなく「よく話すフレーズ集を丸
暗記する」という行動に出るだろう。そりゃそうだ。だって英語レベルほぼゼロの人間が、
英語を運用でき、かつ話すレベルまで持っていくなんていう英語マスターレベルに上げる
なんて 1 週間じゃ到底不可能だ。となれば、よくあるフレーズを覚えてなんとか戦うしか
ない。でも実際これで戦えてしまうのだ。
それはなぜか?理由は"対面で話せる環境にある"からだ。つまり多少のミスやニュアンスの
差についてはボディランゲージをしたり表情で示したり、、、といった感じで上手く合わせ
ることができてしまうので、なんとか伝わってしまうのだ。これなら話す内容の筋を決め打
ちしてしまえば、突破できるだろう。これが"話し言葉"だ。
しかし試験などでは文字で書かれている文章を相手に読解していく必要がある。この時に
ボディランゲージをしたり、ましてや感情を示しても、文字が印刷された紙はただ静寂な反
応を返すだろう。"書かれてあるものを、書かれてある通りに読んで内容を理解する"ことが
求められるのだ。そこには一切の主観や意見を入れてはいけない。これが"書き言葉"である。
そう、もう気がつくだろう。それぞれに持つ性質が違うのだ。だから読み書きと同じように、
何かのやり方を同じようにやって解決、というわけにはいかないのだ。そして、その典型と
して"発音"が関わってくる。
突然だが、みなさんは高校までにいくつの日本語の"字"(ひらがたカタカナ漢字含めて)を
覚えるかご存じだろうか?まぁ現在では常用漢字表にのっている2136字の漢字をやり、そ
してひらがなカタカナで100字、合計して2236字覚えることになる。そう、そもそもこれ
だけ覚えるだけでもかなりのハードルなのだ。英語はアルファベット26文字(大文字含め
てもせいぜい 52 文字)で構成されているのだから、全く初期段階のハードルが違うのだ。
しかしその分、日本語にはあるメリットがある。それが"発音"である。日本語はひらがな50
文字、言い換えれば50音あればいい。まぁもちろん細かい発音のニュアンスに差(雨と飴で
は言い方が違うなど)はあれど、それはもはや慣れていくものでしかない。だから外国人が
日本語を勉強する際、まずは音からやるという人も多いのだ。
ということは、アルファベット26文字で構成される英語は、発音がややこしいことになっ
ていることが容易に想像できるだろう(し、おそらく皆経験しているはずだ)。
ところで、なぜ英語の発音が日本人にとって厄介とされているのか?それは日本人とアメ
リカ人では音の認識の違いがあると言うところにポイントがある。え?どういうことかっ
て?人間の脳みそは右脳と左脳で分かれています。最近の研究によると右脳では感情とい
った情緒の部分を、左脳では論理の部分をとっていると言うことがわかっている。そして、
どの音も必ず子音と母音を組み合わせたものである。
そして、この子音と母音の音の認識は、聞く人々によって異なるのだ。日本人は子音を情緒
に、母音は論理のほうに入れて脳が認識する。例えば皆さん、夏の時期に鈴虫の鳴き声を聞
く場面を想像してみて下さいな。鈴虫が「RRRRR」と泣いている時、我々は「あぁ夏だな
ぁ」と思っている。その理由として、それぞれの音は子音中心であるのが肝である。我々日
本人は子音を情緒として捉えるので、良い音と認識するのだ。
ところが打って変わってアメリカ人に鈴虫の鳴き声を聞かせていい音だよねと聞こうとし
たら、アメリカ人は殺虫剤を持って鈴虫を倒そうと戦闘態勢に入っているのだ。我々からす
ると奇妙とも思える行動を取るのはなぜかと言うと、英語を母語とする人たちは子音を論
理のほうに入れ、母音は情緒のほうに入れて認識してしまうからだ。つまり、彼らからして
みれば、子音が聞こえたとき、それは意味のある音でなければいけないはずなのに、ただひ
たすらとなっている様子は非常に不気味であるということだ。まぁ我々からしてみればこ
れは変だなぁと思うかもしれないが、例えば突然いきなりセミが「あああああああああああ
あ」と言い出したら何をするだろうか。おそらく殺虫剤を持って倒そうとするだろう。まぁ
そう言った具合で、我々は音の違いとして認識の違いもあると言うのが大切だ。
もう一つ別の例をやってみましょう。皆さん、魚・刀・狐と聞いてこの3つの中から同じっ
ぽい2つのを選べ、と言われたらどれを選びますか。
この質問を日本人にすると、ほぼ全員が魚と刀と答えます。その理由は単純で魚(SAKANA)
と刀(KATANA)は同じ母音の”あ(A)”が入っているかです。ところが打って変わって英語と
母語とするアメリカ人とかに同じ質問をして、さぁどれを選びますかと聞くと、ほぼ全員が
刀と狐と答えまる。その理由は刀(KATANA)と狐(KITUNE)は共通の子音の発音”K・T・
N”があるからだ。
つまりこういった具合にして子音の方が大切というのが明確に現れてくるのだ。例えば英
単語にもこれを現れている。沈むの”sink”と考えるの”think”は全く違う発音だ。でも我々は
母音に着目してしまうため、同じ「シンク」と音が聞こえてしまう。だから我々は単語の勉
強する際、まず大事なこととして”子音のほうに注意をして聞かなければならない”というの
がある。多くの単語の発音のルールとして着目されやすいのは子音の音だ。その理由は今語
った内容で明らかだと思う。
そしてここにもう一つ考えなければいけないこととして”文として発音する際にはそれはま
た別のルールがある”と言うことだ。例えば”キャン”と発音する英単語は?といわれたら、
おそらくほとんどの皆さんはできるの「can」だと思うだろう。だが、文で発音する際に
は”can't”と同じ音になる。で、なぜこんな発音になってしまうのか、その理由は普段皆さん
が聞いている単語の発音は”強形”と言われる方だ。一方、今言ったような発音の変化をして
いくものを”弱形”という。そして何が厄介かと言うと、これは知らないとできないと言う致
命的なものがあるので、しっかりそういったものは覚えていかなければならないと言うの
は注意しておこう。
そしてもう一つ大切なことが残っている。それは”リスニングは伸びのスロースターターが
ある”ことだ。文字で読む書くと言うのは、文法を学び、全体を捉える発想で解釈を行い、
それをつなげてしっかりと読んでいけば”読む”と言う行為ができ、それを応用すれば”書く”
と言う行動ができるわけなのだ。だからちゃんと勉強すれば半年近くで行えてしまうわけ
である。
ところがリスニングと言うのは(変な話にはなるが)、より能動的な学習が求められる。と
いうのはほとんど皆さんは文字の英語の勉強をしているというのがあるので(もちろんこ
の”読む書く”学習もしっかり行ってあるのが前提だ。それも忘れて”聞く話す”の学習をやら
せようとする”マヌケな学習”((ましてや初期段階から四技能をすべてやらせようとする、思
考停止の”カス”学習も同じことだ))は実行するに値しない)、そこから音を通じた学習と言
うのは自分で行わないとできないと言うことだ。しかも厄介なのは英語の音と言うのは普
段聞いているわけではないので、たくさん聞いて音を聞いて慣れていくと言う行為にまず
は慣れなければならない。そして最大の山場は、そんな簡単に伸びるわけではないというこ
とである。音と言うのはやっぱり認識していかなければいけないものであり、聞いている量
がそれこそネイティブと比べてしまうとどうしても少ないわけである。
だからそれこそリスニングは半年かけてもあんまり伸びないのだ。それでもめげずに努力
し続けて英語を聞くと言う作業を行えるかどうか。そしてそれを頑張って続けていくと 7、
8 ヶ月目ぐらいにだんだんだんだんと聞けるようになっていき、1年経つとおおよそ大体聞
けるかなと言う状況になっていく。だから、ここまでリスニングを伸ばすと言うのは大変で
あるが、それをわかっている上で逃げずに音を聞き繋げて勉強していくと言う根性を必要
であると言う事は特に意識しなきゃいけないのだ。
というわけで、これで一通りリスニングについては話をすることができた。そして改めて勉
強の全体像を見直してみよう。(まぁ前に書いたものを乗せ直すだけだが。ん?見覚えがあ
るって?さすがだ、また同じことをしようとしているの見透かされてしまった。まぁ前に書
いたのはやり方についてだったので、今回はそれぞれの意義について話そう。)
⓪基礎英単語の一語一訳
まず英語という未知の”記号”(0からやる人にとってはそう見えるだろう)を解き明かすに
は、”英単語”という認識がわからなければ何も始まりません。数学でいう”数字の読み方”を
覚えるようなもので、これが英語の0からの土台になる。たとえば『apple=名詞 りんご』
『go=動詞 行く』みたいに、まずは単語を見たら意味が“パッと”出てくる状態を目指すこ
とだ。
①中学英文法
ここは先述したように”文法用語が出てきた時にアレルギーが起きないように対策を仕掛け
ると同時に、それぞれの文法単元のある程度のニュアンスは掴んでおいてほしい”と書いた。
さて、なぜそんな意義があるのか。
突然だが、この話は”架空の国JAPAN”に起こったことである。とある「ちゃんと英語学の
修士号持ってる」人がネットに以下の内容を書いたのだが、ひとまず読んでみてほしい。
@@@ここから@@@
今日は珍しく英語教育の話をします。
みなさん、中学校で「5文型」習いましたか?私はあれが大嫌いです。だって、文法的に間
違っているので。教科書や参考書にあの「5文型」が載っているせいで英語の教え方にとて
も苦労しました。そもそも教科書ではis, am, areを動詞として扱ってしまっているので、生
徒の頭の中がごちゃごちゃになっていました。みなさんはそんなこと感じたことないです
か?
では、質問です。
I was an English teacher.
この文法をSとかVとかCとかOとかMとかに分類してください。
まあ、いわゆる「第2文型」ってやつですよね。
じゃあ、I taught English.はどうでしょう。
いわゆる「第3文型」です。
ではI was an English teacher.を疑問文にしましょう。「私って英語の先生だったっけ?」
これはVをSと入れ替えたら文法的にOKですね。同じようにI taught English.も疑問文に
してみましょう。「私って英語教えてたっけ?」
Taught I English?
これは文法的にダメですよね。(伝わりますが。)
この時点で「5文型理論」は破綻しています。肯定文のことしか想定していない。そんな理
論を子どもに教えてどうするんだ! っていうことです。
先ほどの文を否定文にしてみても「5文型理論」が破綻していることが分かると思います。
I was an English teacher.→I was not an English teacher.
I taught English.→I taught not English.
(これで十分伝わりますけどねw)
とにかく「5文型理論」は否定文、疑問文では破綻します。
@@@ここまで@@@
いやぁ、実に面白い内容であった。ここまで”お笑い”を展開させてくれる人はそうそうない
だろう。なお私はあまりにもおもしろくて、いてもたってもいられずこの内容を某ChatGPT
に評価をさせてみたのだ。すると以下の通りだそうだ。
&&&ここから&&&
この文章について、論理構成・言語表現・内容の正確性・教育的観点など、複数の観点から
徹底的に評価します。評価後、必要に応じて改善案も提案します。
【総合評価】
主張の明確さ:★★★☆☆(3/5)
論理の一貫性:★★☆☆☆(2/5)
専門性・正確さ:★☆☆☆☆(1/5)
読者への説得力:★★☆☆☆(2/5)
教育的価値:★★☆☆☆(2/5)
①【内容面の評価】
●良い点:
自身の英語教育経験に基づいた問題意識が伝わる。
「5文型」理論の限界を、具体的な英文例を使って説明しており、読者に考えさせる構成に
なっている。
●問題点:
1.「5 文型は文法的に間違っている」は事実ではない
**5 文型は、英語の「文の構造」や「動詞の目的語・補語の種類」などを整理するための“分
析の枠組み”**です。肯定文だけにしか使えないという批判は、そもそも5文型の意図を誤
解しています。
5 文型理論は、疑問文・否定文の生成そのものを説明する理論ではありません。SVO・SVC
といった文の骨組みを示すだけで、それをどう疑問形や否定形に変えるかは統語論や語順・
助動詞のルールの話です。
2. 疑問文・否定文が5文型で説明できないという誤解
たとえば、「I taught English.」は第3文型(SVO)ですが、疑問文「Did I teach English?」、
否定文「I did not teach English.」も同じく SVO 構造を保っています。
「taught I English?」がダメなのは、文法の語順(助動詞が必要)ルールが違うからであり、
5 文型とは関係ない問題です。
3. 「is, am, are は動詞として扱うべきではない」という主張の曖昧さ
「be動詞」は英語文法上れっきとした動詞であり、述語動詞 (main verb) に分類されます。
「状態を表す動詞」という扱いです。
これを否定することは、英語学そのものの基本枠組みを否定することになるため、相当な理
論的根拠が必要です。
②【論理構成面の評価】
●構成上の問題:
感情的な言い回し(例:「教えてどうするんだ!」)が多く、読者が冷静に理解するのを妨げ
る可能性があります。
「この文はSVCだから、疑問文にするとこうなる」など、形式の説明と語順の文法的説明
が混同されていて、主張に一貫性がありません。
③【言語・文章表現面の評価】
「w」「どうするんだ!」など、カジュアルさが強すぎて、学術的・教育的な信頼性を損なう
恐れがあります。
読者の理解を促すための丁寧な説明や補足が不足しており、誤解を招きやすいです。
�
�【改善案】
あなたの問題意識(中学生が混乱しやすい、文法説明が不親切など)には一定の妥当性があ
ります。その方向性を保ちつつ、次のような建設的な修正・補強をすると、読者にとってよ
り有益な内容になります。
&&&ここまで&&&
なんと優しいことだろう。まだ改善点があると言ってくれているではないか。さすがは某
ChatGPTだ、お世辞がうまいこと、、、。では、私がはっきり引導を渡してやろう。この内容
は”0点&英語学の修士号は剥奪レベル”だ。
そして読んで気が付いただろうか?そう、ここに書いてある内容は全て中学英文法の範囲
で話をしているのである。にもかかわらず、この記事は、文型理論と助動詞の疑問文を混ぜ
ようとしていると言う超越(つまり駄作な)理論を展開しているのである。
もちろんこの内容について突っ込みたいことは数えきれないほどある。だがこの内容を読
んでいる人たちは、こんな”救いようのない”状態にならないように中学英文法をやるんだ、
と心がけてくればよい(まぁあくまでも架空の国JAPANの話なので、まさかこんなことが
現実に起こるはずがないと思うが、、、。起こったとしたら、早急に大学の質について議論す
べきだろう)。
②"単元別の"英文法
増量追記の初めに書いてから遥か彼方の忘却のところに置いてきてしまった方もいらっし
ゃるかもしれないが、最近どんどん出版されている、有名講師の分厚い英文法の参考書につ
いて書こうと思う。これはもちろん優れているのは間違いない。各単元の事についてしっか
りと説明をし、先生によっては中学英文法の範囲を少し掘り返しながらもやってくださっ
てるものもあるので、忘れかけていたところに手をかけると言う意味では良い点だろう。
だか今の話を聞いてこの参考書たちはどこに分類されるのかというのを思いつけなかった
人、もう一回このレビュー最初から読んだほうがいいですね。そう、この話は最初から一貫
して言っています。ほとんどの英文法は”単元別の英文法”なんです。そして実際読んでみる
と、結局は単元別の英文法になっています。もちろんこれはやってほしいと言うのはありま
すが、これで「英文法は終わりだ!」と思ってしまった瞬間に撃沈し、英語学習が崩壊して
いくことになる。そこのところはしっかりと忘れないようにしてほしいと思います。ちなみ
にこういうことを書くと「そういえばこの思考する英文法は、②と③を組み合わせたものだ
ってお前は言っていたじゃないか。だったら、この一冊で済ませるのがいいんじゃないか
い?」と言うことを思う人がいるかもしれない。実はこの指摘はあながち間違ってはいない
のだが、ある点で欠落していることがある。それは抽象化能力の話だ。富田の英語で全てを
済ませると言うのは、この抽象化能力の観点から見れば害でしかないと言うことである。
どういうことかって?例えば皆さん、好きな料理に固執している人に、他の料理を正しく判
断することはできるでしょうか?いやー、そんなことはできるものではないでしょう。別の
視点から見れば、おいしい部分や良い部分を見つけることだってできるはずなのに、それを
わざわざしたがらない人間がまともな判断を下せるわけはないんですね。
これと同じことで、ただ 1 人だけに全てを捧げてしてしまうと言うのは、言ってみればや
ってみる事は宗教と変わりないです。まぁよく富田信者と言われてしまう人がいるのだが、
それはあくまでも多くの講師に付き合ってきて富田先生を中心にしたたちのことを指して
いる(と思いたい)。だから皆さん、他の講師から得られる視点と言うのはあります。しか
もそれはは単元別だからこそ生かされるものもあります。だからそういう別の視点から見
て得られるものもあるので、しっかりとそこは吸収してきてください。そして次の段階に進
むわけだ。
③"現象別の"英文法+英単語学習
まぁ結局段階を担当できるのは”思考する英文法”や、"1つの表現には様々な可能性が含まれているので注意せよ"と唱えてもらえるものぐらいだろう。ここの段階は、それこそ 1 番最初に書いたレビューで語り尽くしているような気がするので、ここではちょっと別の話をしよう。
よく「富田先生の著書は説明が長くて見ていられない。短いものこそが、正義」と言った、
これまた間抜けなレビューが見られることがある。だが、その人は忘れてはいませんか。”
人間はかなり複雑なことを考えながら、物事を決めていっている”と。そんなのは今英語を
勉強して皆さんであればわかっているはずなのですが、わかっていない人もいらっしゃる
のが悲しいところです。
確かに我々が日本語を使っているときはそこまで苦労していません。普通に不自由なく使
えているように思うでしょう。ところが外国人が日本語を勉強しようとすると、かなり苦労
しているのは皆さんも知っていることであるでしょうし、音のアクセントをしっかりと生
かすのをできている人はあまりいません。同じように我々日本人が英語を勉強している時
も、英語を身につけるだけではかなり大変であり、話すとなってくれば、これは厄介なこと
間違いありません。つまりこれが意味する事は”言語と言うのは体系はしっかりしているが、
それを決めていくステップはかなり複雑であり、それをしっかりと見極めていかなければ
いけない”ということがわかる。
そして言ってみれば、富田先生の説明は、この複雑なステップをしっかり余すことなく丁寧
に説明しているに過ぎない。つまり富田先生を説明を否定する人は、人間の考えるステップ
を全て指定しているやつと同じことでなり、それは通称間抜けと言うことになりますね(以
上証明終わり、Q.E.D.である)。なのでそういう言い訳をせずにしっかりと学習に向き合っ
てほしいと思います。
④長文and英作文
英作文はともかく、まぁ普段英語を読む際に問題を解くことを意識しながらやると言う状
況は普通ではない。だからあくまでもこの段階は解法特化であると言うことに注意が必要
である。
あっそうだ、たまにとんでもない勘違いが発生にするから一応言っておくと"英文解釈と長
文には違う読み方などない"。もちろんパラグラフリーディングと言った類の読み方は、読
む上で一定の指針としてはなりうるかもしれない。それで読みやすいなら、そういう考え方
も使ってやってみてもいいだろう。
しかし実際に本文を読み進める上で、やる事は一つしかない。それは"筆者との対話"である。
実際、試験問題で我々が読む文章は論説文や説明文が多い。ということはまずは論説文、説
明文を読めるかどうかが肝になるのは百も承知だろう。
で、その流れはおおよそ決まっているのだ。論説文なら、ほぼ確実に世の中の意見に対立し
ようとする筆者の意見がある。で、筆者の意見は最初にでてきやすい。そうなるとそこを読
むと必ず疑問がわく。"なぜそう考えるんだ?"ってね。そう、そう思って次以降の文章を読
みに行き、その疑問を解き明かすことが"筆者との対話"なのだ。説明文ならもっとわかりや
すいだろう。その手の話はある物事についての説明だから、最初の段階では確実に"わから
ない"のだ(まぁもしかしたらたまたま知っていることがでるかもしれないが、それは単な
る偶然に過ぎない)。ならばそのまま文章を追っていけば"わからない"から"わかる"になっ
ていく。
まぁもちろん実際に"筆者との対話"は、生身の状態でやるわけではない。それでも筆者には
"言いたいこと"があるから文章を書くのである。ならば我々の仕事はそれを正しく"理解す
る"のである。それをするのが"読む"ことなのだから、それを念頭に考えると「英文解釈と長
文は読み方が違う」なんて発想は毒でしかない。
なお小説の場合は間に心情を補って読む必要があるため、評論文や説明文に比べると読む
ハードルは高めである。それでも"補う"段階にまで持っていくにはまずしっかり構文が取れ
て訳ができ、説明を追っていく姿勢は変わらずである。
まぁこの話はどちらかと言うと②の時に言っておくべきことだろう。そして前にも書いた
が、③までの段階で”英文は時間をかければ読める段階にいる”ことが大切である。
⑤リスニング
ここは話したのでカット(なんとまぁ清々しい)。
というわけで、そんな感じで皆さんのガイドに少しでも役に立てたら幸いだ。
そうだ、最後に話しておきたいことがあった(まだ話したいことがあるのかって?まぁどう
せここまで書いちゃったんだからちょっとだけ付き合ってくださいな)。
最近レビューを見てみると「単科の付録の方が良かった」と言う風な話がたくさん出ている
のだが、私はその人たちに聞きたいんですよ。あなたほんとに富田先生を授業を受けていま
したか?と。
1 番最初レビューでも書いたが、この”思考する英文法”はもともと授業の部分と単科の付録
を合わせて 1 つのものになると言うことだ。つまりどちらかだけでは意味がないのだ。現
象別の英文法と単元別の英文法を合わせて”富田の英語”が完成するのだ。つまり付録が良か
ったと言っている人たちの話は「単元別英文法だけで済ませれば良い」と言う話になってし
まうので、せっかくの良さをつぶしてしまうことになる。だが、まぁ1つ悲しい点があると
すれば付録は削除されてしまうのでどんな中身なのかわからない人もいるだろう。一応そこの点を解消するために一通りの要約を乗っけてみようと思う。 まぁただ内容をみてみると、付録に固執している人たちは持ち上げすぎているというのが感想だ。
第一学期→まぁここは単元別の英文法である。
夏季講習→ここはあくまでも1学期の復習の立ち位置なので、単元別の英文法と言ってい
いだろう。
第二学期→1学期の内容を生かしつつ、復習しながら語法の知識をつけていくのがメインで
ある。
冬季Ⅰ期→これまでの知識の総復習がメインである。
冬季Ⅱ期→知識、観察力の総復習と語彙のドーピングをするのがメインである。
というわけでこんな書き方をしたという事は、おおよそ察しがつくとは思うのだが1学期
の付録をフォローしていくと言うのがほとんどである。まぁ最後の冬季Ⅱ期だけはすべて
の総復習と言うメインがあるので、ちょっと毛色が異なるが、まぁそういう位しか違いがな
いと言う事は、皆さんから見ても明らかだろう。だから皆さんもそんなことは意識せずにこ
の”思考する英文法”に格闘していただきたい。
(−_−;)増量追記終了(−_−;)
というわけでだいぶ長いレビューになってしまった。もし読んでくれたら(本当に読む人は、
暇人か変人か真面目な学習者かだろう。ぜひ、3者目に届くことを祈りたいが、、、)幸いだ。
最後にこの本を使って英語を身に着ける人たちと、新たなる家庭と子を授かった富田一彦
先生に感謝を込めて。
⭐Seize the day!

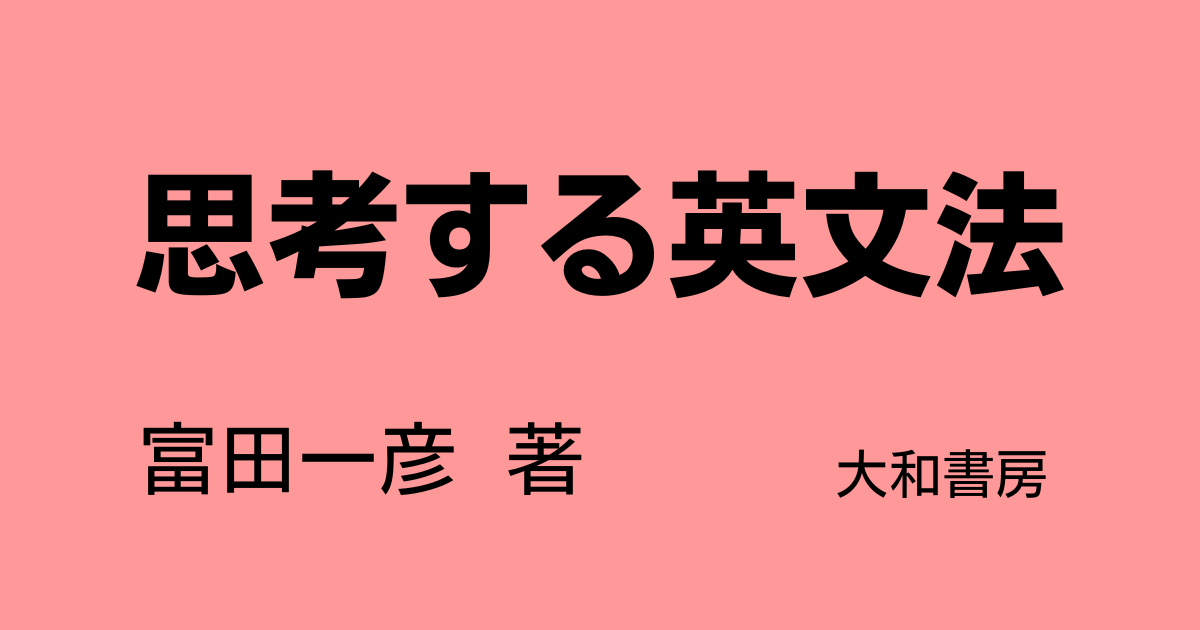

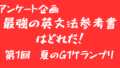
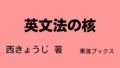
コメント