駿台予備学校の関西英語科主任を務めた表三郎師の訃報が伝えられました。
表三郎師は1940年広島県生まれ、大阪府育ち。二浪で甲南大学経済学部に入学し、大阪市立大学大学院経済学研究科博士課程修了。
大学時代は学生運動に参加し、「大阪市立大学全学共闘会議議長」だったそうです。
桃山学院大学の非常勤講師を務め、マルクス経済学の論文を多数執筆しています。
その後、駿台講師になって、1976~1991年まで関西地区の英語科主任を務められました。
「ポスト構文主義」とは何か?
表三郎師の参考書と言えば、『スーパー英文読解法 上・下』(論創社)です。
この本では、英文解釈研究のスタイルを「ポスト構文主義」と称していました。
表師によると、従来の英文解釈は
1 単熟語・公式主義
2 構文主義
の二通りだったといいます。
1の「単熟語・公式主義」は山崎貞 著(佐山栄太郎 改訂)『新々英文解釈研究』(研究社)に代表されるもので、日本人(日本語話者)にとって訳しにくい構文を「熟語」「公式」として整理するという、昔からある方法です。
2の「構文主義」の代表といえるのが伊藤和夫師です。伊藤師は「単熟語・公式主義」を批判し、英文の構造分析と「左から右へ」読む方法を提唱しました。
その伊藤師の「構文主義」を発展させたものが「ポスト構文主義」でした。
表師は伊藤師を批判していましたが、実は「構文主義」を否定したわけではないのです(そもそも「公式主義」から「構文主義」へというのが「伊藤和夫史観」に乗っかった歴史認識)。
むしろ「構文主義」の〈構造分析〉を徹底したうえで、〈表現分析〉〈内容分析〉に踏み込んだのが「ポスト構文主義」ということなんですね。
その方法は天満美智子 著『英文読解のストラテジー』(大修館書店)の影響を受けたものであると「はじめに」で書かれています。
構文を分析するだけでなく、パラグラフ分析や内容理解を重視するというのは今となっては珍しくありませんが、これらを早い段階で取り入れていました(パラグラフリーディングはこの本以前から受験参考書で取り入れられていましたが)。
そのほかに、ビデオ講座やカセットテープ教材も販売されていましたが、残念ながら現在では入手困難となっています。
なんとかDVDや音声ダウンロードで再販してほしいものですが、難しそうですね……。
駿台関西の「生ける伝説」
表三郎師といえば、参考書以上に駿台での講義で強いインパクトを残したと言われます。
経歴からわかるように、マルクス主義の研究をしていた左翼思想家で、講義でも左翼思想にもとづく雑談が多かったそうです。
「右も左も分からない生徒達に英語で左を教えてくださる」というのがネットでの皮肉めいた評価でしたw
ただ、それでも表師を慕う受験生は多く、関西の駿台では毎年多くの表三郎信者=サブラーが生まれていました。
講義での雑談も全くの無駄話というわけではなく、深い教養と知識量に裏付けられたもので、英文の深い理解につながるものだったと言われています。
その知識の一端は『スーパー英文読解法』のCoffee Breakのコーナーでも披露されていますが、ただ知識をひけらかすのではなく英文の内容から発展して教養を深める「雑談」が展開されています。
また、表師は意外にも実用書のヒット作も書かれています。
その一つである『日記の魔力 この習慣が人生を劇的に変える』(サンマーク出版)は、日記によって日々の行動を意識化するというもので、非常に実践的でありながら表師の教養も垣間見える隠れた名著といえるでしょう。
その人柄や話術で多くの受験生に愛された「生ける伝説」表三郎師。また一人、予備校界のレジェンドがこの世を去ってしまいました。フォーエバー表三郎。
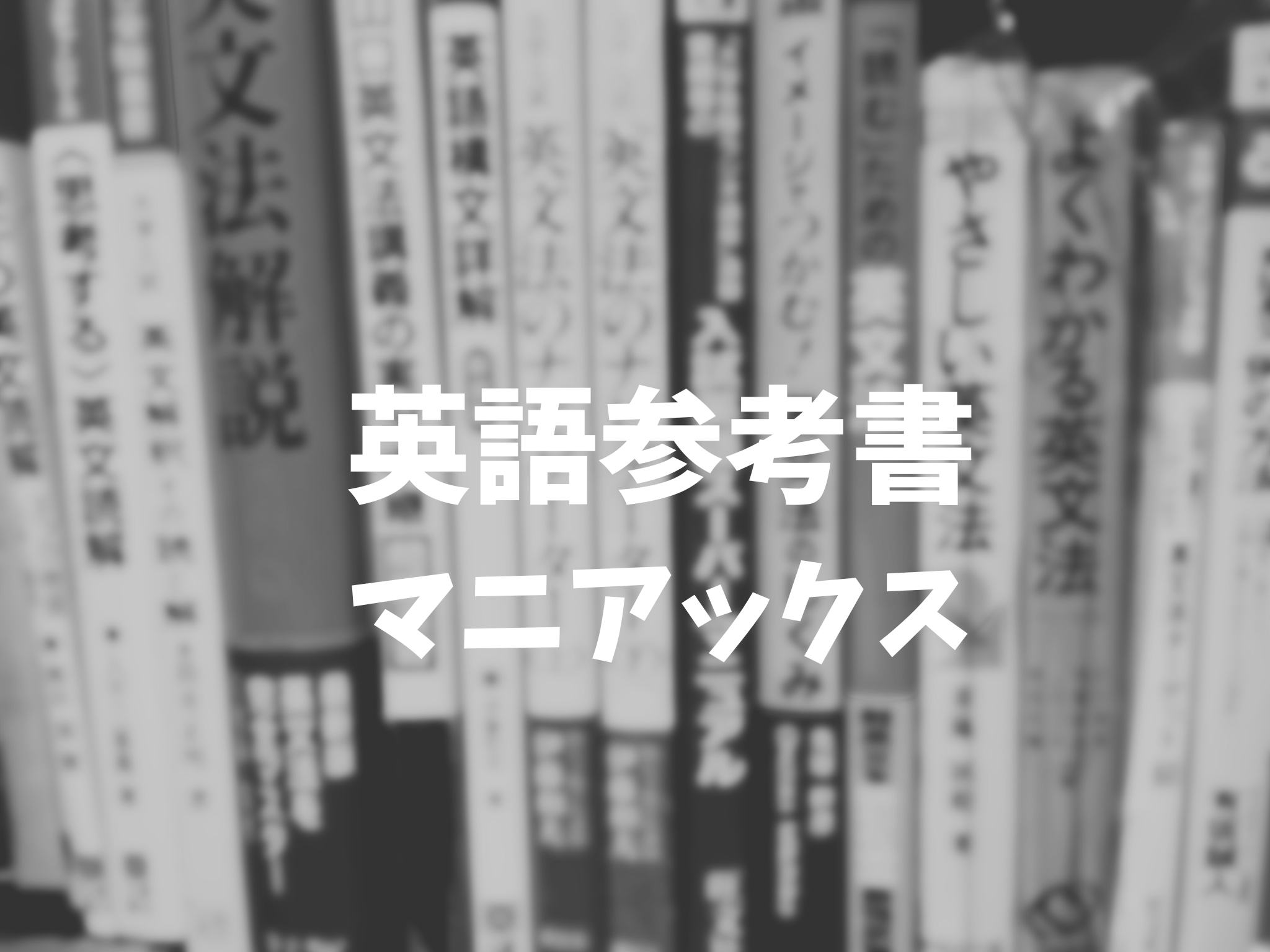





コメント